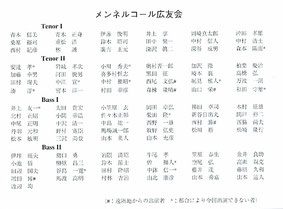第11回定期演奏会
1993年2月27日(土)6:00PM 開演
新宿文化センター・大ホール
I. Missa Salve Regina Pacis
Heinrich Huber 作曲
指揮 牛尾孝
オルガン 辰巳美納子
Kyrie・Gloria・Credo・Sanctus・Benedictus・Agnus Dei
♪
II. 男声合唱組曲「蛙の歌」
草野心平 作詩 堀悦子 作曲
指揮 牛尾孝
ピアノ 辰巳美納子
♪
III. The Favorite Songs of the World
・Robert Shaw Choral Series
指揮 牛尾孝
Loch Lomond・When You and I were Young, Maggie
Du, Du Liegst Mir im Herzen・La Tarara
Marianina・Stodole Puapa
♪
IV. 男声合唱組曲「若しもかの星に」
百田宗治 作詩 多田武彦 作曲
客演指揮 北村協一
ごあいさつ
代表:伊藤 俊明
年輪を刻むように、本日第11回定期演奏会を迎えました。ご多用の中、ご来場下さいました皆様に厚くお礼申し上げます。
切れ目のない年ごとの積み重ねの中に、いささかの変化と進歩を求めて活動を続けて参りましたが、幸いにも昨年は前年度に引き続き、東京都合唱コンクールで上位入賞の栄をいただきました。遠く10余年を顧みるとき、上り坂を一歩一歩踏みしめながら、やっと小さな峠に辿り着いた心境です。しかし上を仰ぎ見れば、合唱の道は高く険しく、伝統のある合唱団に比べればまだまだ若齢と言わざるを得ません。
ようやく組織作りと合唱の土台作りの方向を見いだしたいま、次なる目標は「深く味わいのある合唱づくり」「心に残る演奏」であります。おこがましくとも、この目標に向かって、年齢や仕事を越えて社会人の生きる姿をぶっつけつつ、励んでゆきたいと思います。
私たちのこの様な思いに対して、昨年もまた諸先生方の熱意溢れるご指導をいただきました。魔術師のように声を引き出してくださる大久保昭男先生、合唱の造形の深みに私達を導いてくださる北村協一先生に加えて、服部洋一先生には世界民謡の言葉の発音とフレージングをご教授いただき、更に多田武彦先生には詩と音楽のかかわり方について明快なご教授を賜りました。4人がかりでご指導いただく、この願ってもない幸運に対し、本日の私達の演奏はそれ程のお応えできるものか、いささか不安なしとしません。しかし団員一人ひとりがまた新鮮な感動を抱いて本日の演奏に臨むことができましたことを思い、諸先生方のご指導に対し、哀心より感謝申し上げます。
10余年の年月の経過の中で、激動の社会に身をおく私あち一人ひとりには、少なからず変化がありました。しかし広友会はいつの時代にも健全に守られ続けて来ました。これは本日ご来場のみなさま方の変わらぬご支援と、団員ご家族の温かいご理解があったからにほかなりません。どうかこれからの1年もまた、従前にも増してご助言とお力添えを賜りますよう、心からお願い申し上げ、ご挨拶と致します。
「蛙(堀悦子)」解説
「蛙」の詩をテキストとした男声合唱曲は数多い。それは、草野心平による蛙の詩群自体が、音楽を要求しているからであろう。蛙に言わせれば「コーラス!コーラス!コーラスは
俺達の合言葉(スラング)!」(「行進曲」詩)なのだ。
その蛙たちは草野心平の詩の深化にともなってあるいは哲学的に成長し、
あるいは特殊な能力をそなえてゆくのだが、堀悦子氏がピアノ伴奏による男声合唱組曲の
ために選んだのは、生や死や性、歓喜や悲嘆、そして冬眠と、原初的な蛙の感情を
歌い上げた、初期の六篇の蛙詩であった。よろこびにせよ、かなしみにせよ、
テーマが単純であるだけにより深く力強い音楽表現が求められるのではなかろうか。
人間社会の戯画であることを頭の片隅に置きながら。
1.いぼ
春になって真っ先に地上に出てくるいぼがえる。擬人化した「春」を相手にぶつくさ喋り
ながら歩いているところが滑稽である。
この詩は初出では、福島県磐城地方の発音をとどめタイトル「えぼ」で、
「ぼくたち仲間だ/大円の春の地べたに最初に声をあげるぼくたち仲間だ/
青や赤や雨なんかもそのうちにはひ出してくるだらう/他の兄弟に魁けて唄ひ出す
ぼくたち仲間だ」などと、仲間意識・地に根差した階級意識が濃厚であったが、
改訂によって蛙の春情に主題がうつされている。「そつちでもこつちでもぶつぶつ
なんか鳴き出した」のは先に交尾を始めた蛙であり、だから主人公は「やりきれんな」
と繰り返すのであった。
2.青イ花
蛙の天敵は蛇と人間の子供である。この「青イ花」の場合は、まだ世の中をよく知らない
幼い蛙が、蛇の腹の中から母親蛙に残したメッセージである。
子供らしい片言をカタカナで表現している。その子は自分の「死」を理解できず、
青い花のような、それでいて燃えるような麻痺の感覚を蛇の逆歯の毒のために
味わいながら、もう帰れないことだけは感じているのである。幼いが故の天国的な死。
3.河童と蛙
月は生き物の狂躁状態を誘う。この河童は、大河童沼にて満月を愛ずるあまり、
日頃鍛練のシンクロナイズド・スイミングの披露に及んだ。
デュエットのお相手は水面の月。ぐるりの山と蛙が観客であった。
水の上に立ち上がるウルトラCのあと、直立に沈む鮮やかなヒキ。
沼は月の「兎と杵の休火山」まで映るような静けさにもどった。
「ぐぶう」、蛙のブラボーである。
4.蛇祭り行進
蛙の社会にゲリゲという名のカリスマ的ヒーローがいた。彼は敢然と蛇に挑み、
しばしば蛇を斃した。勝利の夜はお祭りである。蛇をほふる大パレード。
蛍を口に含んでの提灯行列。たくさんの蛙のとりどりの歓呼。
風や星が祭りの装飾のようである。おしまいにはロンドの群舞だ。贄の残酷さに比例して
群衆の喜びは盛り上がる。蛇祭り行進は、<祭>の本質的エネルギーに満ちている。
5.おれも眠らう
冬眠態勢に入った二匹の蛙が、土の中でつぶやくような会話をかわしている。
「るるり」の蛙が一度鳴く。「りりり」の蛙が一度鳴きかえす。三回繰り返し。
四度目の「るるり」。返事がない。促す「るるり」。やっと「りりり」と返事。
また「るるり」。返事がない。「るるり」。まだ返事がない。「るるり」。
すると「りりり」。この反応の鈍さじゃあ、もう相当眠いんだな。そんなら「おれも眠
らう」。蛙語版の「秋の夜の会話」である。
6.祈りの歌
この曲では詩の前半の状況設定の部分が省略されている。
「ごびろ」という名の蛙は生死の境をさまよい悪夢にうなされている。
その恋人の「りるむ」という名の蛙は祈りの歌を歌うしか手立てがない。
「りま りま‥‥」嘆きの歌。「死ぬいや、死ぬいや」の叫び。
しかし、最後にはその歌も微妙に変わる。
「いいる いいる おお いいる いいる よう」。
この時、「ごびろ」に死の安息が訪れたようだ。
『若しもかの星に』 解説
百田宗治は、1893年大阪市西区の商家の末っ子に生まれた。本名、宗次。若い頃から
フランス文学や短歌にしたしみ、23歳のとき百田宗治の名前で詩集『最初の一人』を出版
した。27歳で東京に移り、雑誌『解放』の編集者をへて詩誌『日本詩人』の中心的同人と
なった。大正末年『日本詩人』が分裂して、百田宗治は詩誌『椎の木』の主宰者となった
。そこには三好達治・丸山薫・北川冬彦・伊藤整ら若手の詩人たちが集まり、百田は良き
指導者であった。しかし、太平洋戦争前後の彼は児童の作文教育に傾倒し、また、一時
陸軍報道班員として中国に滞在するなどして詩から遠ざかり、戦後札幌移住、のちに
千葉県の岩井に転居、1955年肺がんのため永眠した。63歳であった。
初期の彼は時代の思潮に敏感に影響された詩人だったといえよう。その出発は白秋風
の抒情詩だったが、まもなく民主主義運動の文学的あらわれである口語自由詩の運動に
加わる。やがてプロレタリア文学の流れに参加し、世間からは「民衆派」と呼ばれた。だが、そうした立場での彼の詩作は30歳を越えて行き詰まり、やがてプロレタリア文学と訣別して、空想性の豊かな、静かに瞑想するような詩のなかに自らの個性を発見するに至る。
俳句的な観察の影響があるともいわれている。
男声合唱組曲『若しもかの星に』は、百田宗治の生涯にわたる作品の中から6つの詩が
選ばれて作曲され、1978年に初演された。これらの詩の中には、深く思索のうちに沈潜
しながら、ときには孤独を、ときには友愛を感じ、ひとのぬくもりを求めることもあれば、折々は愉快に心を踊らせていた詩人のなまの声があふれている。それは男声四部合唱の音色
で表現されるにふさわしい。
1. 若しもかの星に
冒頭の「もしも、かの星に」と、最後の「もし、吾々の一人が」の二つの仮定表現の枠を
持った構成は、星にただ一人取り残されたその孤独な人間が、ほかならぬ詩人自身である
ことを婉曲に伝えていると思われる。これは百田宗治の初期の観念的な詩のひとつであるが、後期の作に見られる独創的な空想性を先取りしている。
2. 光
百田宗治は若いころインド哲学に惹かれてリグ・ヴェーダを愛読したという。その中心というべき梵我一如の観念の詩化である。絶対唯一神(梵=太陽に象徴される)が、実は個人個人(我)のうちに存在しているという汎神思想である。太陽の光は遠い、しかし、じつはその光は自分の内部にある光と同一である。当時としては、このような思想詩は新鮮であった。
3. 樹のぼり
詩人が39歳のときの詩集『ぱいぷのなかの家族』に収められている。同書は百田宗治の
詩的個性の凝縮というべき代表作で、自由な空想詩に満ちている。また、牧歌趣味と無垢な
子供への志向は彼の特徴。現実に「樹のぼり」したのではなく、想像で純朴な少女と遊んで
いるのであろう。詩人は、子供たちとの交流を通して全人間の魂のつながりを感じ、孤独を
いやしている。
4. 母の夢
文学に入れこんで家族を嘆かせ、故郷である大阪と疎遠になってしまった百田宗治だが、
母親はつねに最後まで気持ちの上での理解者であったようだ。ほかの夢の詩で、母とともに
寂しい街を歩いていたのに母は後悔してどこかへ行ってしまった、という場面がある。わがままな息子を不安定な道に進ませたことがたえず「あたらしい悔い」であり、それでも結局許すことが「いつくしみ」であろうか。
5. 海 景
大正11年正月、30歳の時、百田宗治は房総半島の南端野島崎から館山を通り木更津まで
の旅行をしている。旅中の連作八篇のひとつ。洲崎を回り館山湾が見えた時の印象であろう。
大波璃はかがやくおだやかな海を大きなガラスに誓えたもの。外洋を前にして「壮大と広濶」を感じたあとでは、湾の内ののどかな景色は「ぽつかりとした日だまり」に感じられたというのであろう。馬車のはずみは詩人の旅の心のはずみでもある。
6. 遠いところで子供達が歌ってゐる
子供たちの声を通じて百田宗治が聴いているのは、世界中の人間の魂の連帯である。歌い
、遊び、あるいは争い合う時でさえも、本人たちが意識しなくても、人間は「はるかに支持し合ひ、保ち合ふ」ものだ、ということが主題である。第1曲の「若しもかの星に」では解決されなかった絶望的孤独が、この終曲で救済される。
(深沢眞二)